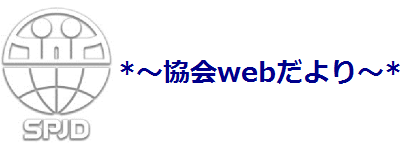4月27日Sat ランプール ~ ロール移動( ロール・スングラ・ランプール街道) ロール1泊
移動途中 ロール手前 Devta Bondra 寺 立寄り
今日から本格的にヒンドゥヒマラヤ木造建築見学の旅が始まる。スピティ&キナウルエリアでのヒマラヤ山岳風景はここで一旦終わりとなり、暫くはヒマラヤの里山風景となる。
標高が下がりリンゴ栽培に適した高度の山を利用した果樹園開発は驚かされるばかりであった! リンゴ果樹園はどんな斜面でも収穫が望める場所には道を設え、棚畑を築いていた。 冬季の積雪、春先の雹対策など自然と闘いながら世界へ輸出するまでに品質を高め量産されている光景を目にした。
リンゴ収穫で農村生活が豊かになり、リンゴ成金を感じさせる民家も目に付いた。そして人々は村に現存する経年劣化して来たヒンドゥ木造寺院の再建に財力を寄付しているように感じられた。
農閑期の時期、私が訪れた村々では寺院再建の手が加えられていた。再建に当たっては手を付けてから3~4年かけて工事が進められるとか? 石積み、石葺き、彫刻、などボチボチ進めているような光景だった。
08:37 ランプール 宿 出発
12:10 サマーコット 休憩 ⇒ 角塔型木造寺院を眺める Lankra veer寺

2:19 Devta Mahshwar Ji 寺 Pujarli ⇒ 近年改築された美しい角塔型寺院を眺める。

2:30 ボンデラ(Bondra)寺 到着 ⇒ 13:52 出発 ⇒ 現在 改築中
長閑な里山斜面を覆いつくすリンゴ畑、その収穫の恵みで潤う農村は信仰に捧げる思いも豊かさと比例しているように思われる。リンゴ御殿が点在する集落の寺院は恵まれたリンゴ畑の中で新たな光を放っているように感じた。

周りをリンゴ畑に囲まれた寺
寺院の境内は広くない割に本堂は大きく、なかなか上手く写真が取れなかった。改築作業は数年前から続けられている様子で改築作業の取りまとめ役と思われる男性は、本堂は500年位経っていると言う・・・ そんな歴史の流れのなか、本堂即ち母屋以外の付属棟が順次完成している状態だった。
カルムやラブラーンでで角塔型木造建築が何時建設されたのかと現地人へ尋ねると、「分からない・・・ 500~600年経っている」と語る。 此処の寺でも500年と言う数字を語った・・・ 分からないことは500で片付けてしまうらしい。

本堂は3層の壁(石を積んだ壁に木の水平材を挿入したドルマイディ構造【校注1参照】)の上にこの寺独特の木造本殿が乗る


完成している付属棟の屋根は鉄平石 ナーガ(蛇)?を刻み込んだ飾窓
4月28日Sun ロール滞在 プジャリ/ダビ・ダール/チルガオン 各村散策 ロール2泊目
Davi Dhar ⇒ Khantu寺 /
Chirgaon ⇒ Raghumath Pawasi寺、
Pujarli ⇒ Rudra Deta寺 その先 Narayan Devta寺(ロール西約26km1時間)
ロールはヒマラヤの里山と言って良いだろう、ヒマラヤの入口シムラ県に属するらしい。リンゴ栽培が盛んな地方は日本で言えば長野、青森と言った気候に似ている感じだ。しかし里山の姿が日本とは全く異なる!
何故この様な地域に独特のヒンドゥ木造寺院が建てられたのか? 調査、研究は手づかず状態とか・・・ 独特の木造寺院は集落の人達によって少しずつ変化を加えられながら何代にも渡って現在まで大事に守り続けられている・・・ 寺院に手を加える作業は決して終わりがない! 寺の祭りは春先、農作業が忙しくなる前に行われるようである。
09:25 プジャリ Rudra Deta寺 到着 ⇒ 10:05 出発
 ルドラ寺の光景 到着前
ルドラ寺の光景 到着前
ルドラ寺境内の建物は現時点で手を加える様な工事はなかったが、寺院入り口前の参道らしき場所には運び込まれた岩石が所狭しと置かれ、石材加工場で石工が黙々と作業を行っていた。
寺院参道エリアの外構工事をするために加工している石材だろうか?
それにしてもおびただしい石材を綺麗に石積した石の壁構造と、長年の経験や新たな発想で生まれた石壁の補強木材を取入れたカトクニ構造【後注2参照】が手を加え、寺院が増築、改築をして来た年代を示す姿が佇む寺院。
ここでも500年位昔に建立されたとか? 元々は木造平屋の寺だったと語っていた。
ルドラとはインド神話に登場する暴風神とか。


寺の入り口 石材加工場 黙々と作業する石工

狭い敷地に目一杯建築された本堂
(右奥に見えるのが初代本堂)
10:40 Narayan Devta寺 ⇒ 11:36 出発
ナラヤンとはヴィシュヌ神の化神でその妃は美、幸運、繁栄の女神ラクッシュミー。
ルドラ寺が佇む斜面の谷を挟んだ向かい側の集落に、ヒマチャール・プラディッシュのヒンドゥ木造寺院の佳作と呼ぶに相応しい近年再建されたナラヤン寺が建っている。
外観の優雅な美しさに加えて木造寺院規模大きさに圧倒された! 建築図面あっての建築か?それとも語り受継げられて来た経験を頼りに建築されたか?分からない。
 移動中 谷越しに眺めたナラヤン寺院の全貌
移動中 谷越しに眺めたナラヤン寺院の全貌


境内から眺めた寺 本殿を中心に左右対称 正面入り口
14:08 ラリーラ 到着 ⇒ 14:53 出発 ラグマータ・パワシ(Raghumath Pawasi)寺
異国人など滅多に訪れないパバー川流域の村「チルガオン」から更に奥深い渓谷に拓かれたラリーラ村は大自然の環境の下で人々はリンゴを栽培しながら暮らしていた。時代の変貌と共に若者は村を去ったのか?
寺を囲むようにして伝統家屋が寄せ合う格好で立ち並んでいた。集落を散策すると、渓谷とヒマラヤが展望出来る小さな広場に婦人達が集まって何やら雑談していた。 私が訪れたことに驚きもしないでニコニコと接してくれた。

16:02 ダビダール 到着 ⇒ 16:50 出発 Khantu寺 ランサール最古にして最強の神とか?
チルガオンからロールへ戻る途中にある渓谷をさかのぼって行くとダビダールと呼ばれる山郷があり角塔型ヒンドゥ木造寺院と正方形平面のカトクニ造建築寺院、二つの寺が山の斜面に建っていた。
この地区も豊かな杉林で覆われているなかリンゴ畑開墾が進んで、現在ではリンゴ果樹園の方が面積的には多くなっているように感じたが、美しい里山には変わりなかった。
カントウ寺(khantu)は改築が終わり、境内の外構工事が行われていた。本堂入口左側に中国領チベットに聳えるヒマラヤのカイラス山の写真を堂々と掲げていたことからシヴァを祀る寺だと思う。
カイラス山の威容を取入れた感じの屋根が天辺に取付けられていた、改築をしている最中に思い付いたのか?改築前の屋根にもあったのか? それともシヴァ神がカイラス山を持上げている神話に因んだ姿を取入れたのか? 想像が広がる。

本殿入口左側にカイラス山の大きな写真が掲げられていた
【後注1】ある程度積み上げた石積壁に木材を水平に敷いて石積壁を補強する構造はドルマイディ(Dholmaide)と呼ばれる。
【後注2】水平材をある間隔で二本並列に敷きその間に石材を押し並べて四方へ井桁状に組む。木材で四方を固めたら再びその上に石を積み上げていく構造はカトクニ(Kathkuni)と呼ばれる。